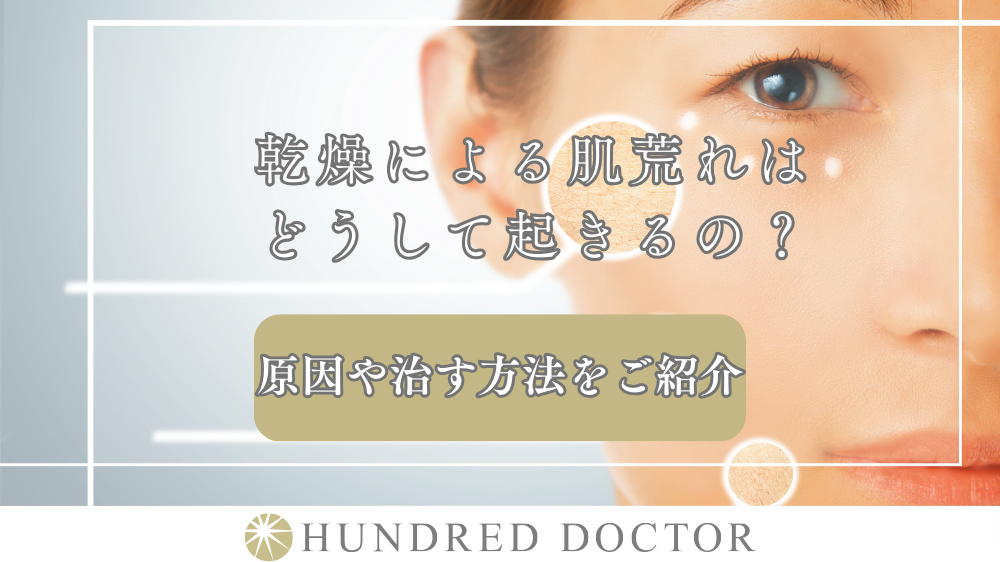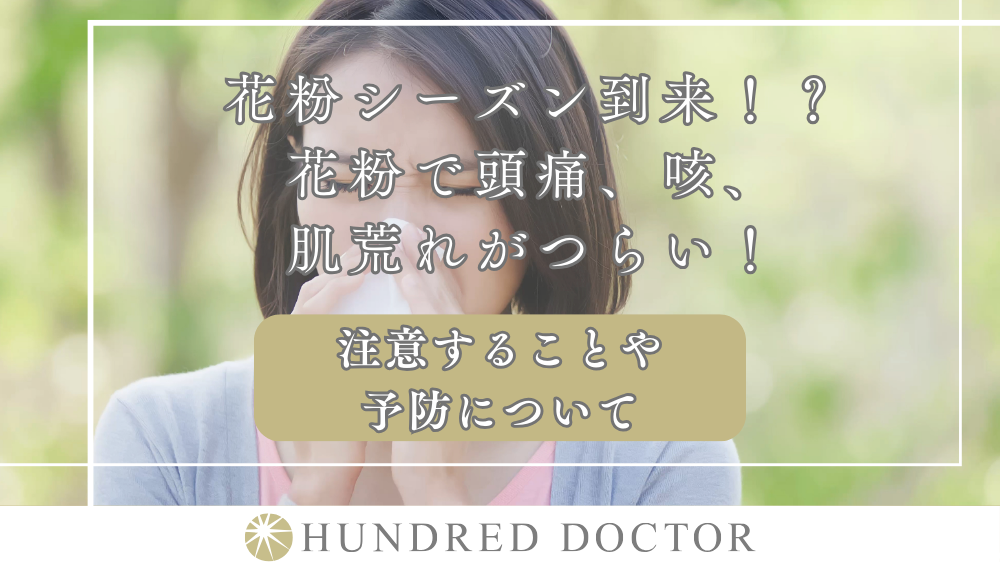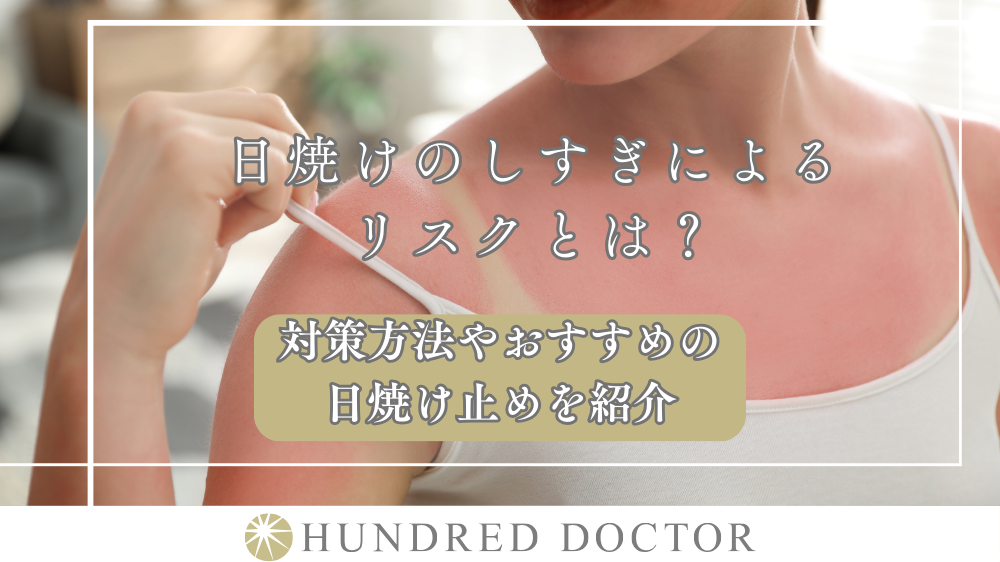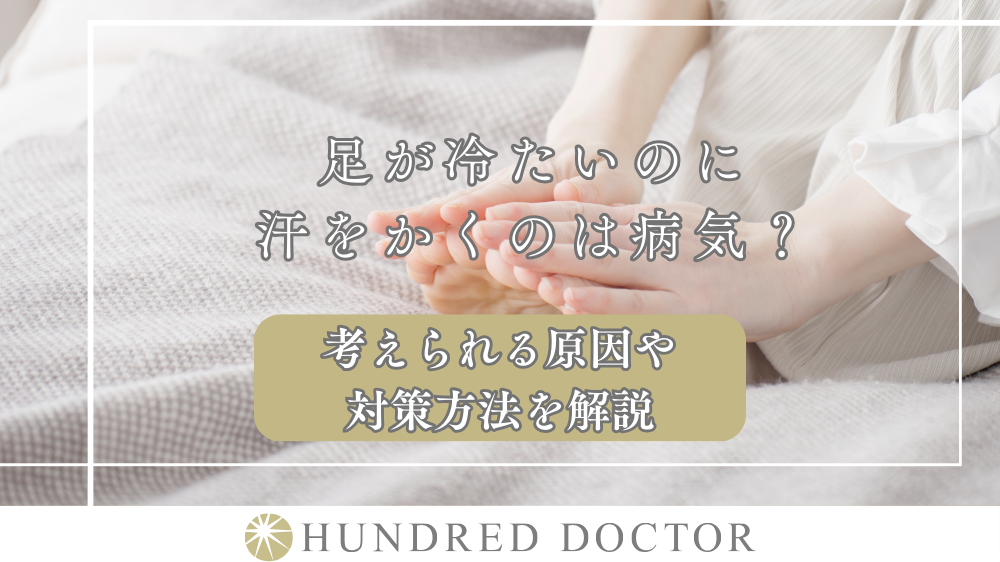
足が冷たいのに汗をかくのは病気?考えられる原因や対策方法を解説
足が冷たい原因の多くは「冷え性」によるものですが、まれに冷え性以外の原因が隠れている場合があります。
さらには男性と女性で足が冷たい原因が異なる場合もあるでしょう。
本記事では、足が冷たい原因や、適切な対策について詳しく解説しています。
足の冷たさや汗をかく際に疑うべき病気についても併せて確認していきましょう。
Contents
男女別の足が冷たい原因

足が冷たい原因は、男性と女性で異なる場合があります。
それぞれの性別ごとに正しい原因を探り、自分に合った対策を立てられるように準備をしておきましょう。
男性の場合

運動不足
運動不足によって血流が悪化すると、末端へ血液が十分に送られず、足が冷たいと感じる原因になります。
さらには加齢によって筋肉や臓器の機能が衰え、新陳代謝が悪くなることも原因の一つといえるでしょう。
筋肉はポンプのような役割を担っており、血液の循環を助け、代謝をアップしてくれます。
週に2~3回、1日20分程度の有酸素運動や筋肉トレーニングを目標にし、運動不足を解消することが大切です。
喫煙
喫煙は肺に悪影響を及ぼすだけではなく、血管にもダメージを与えてしまいます。
タバコに含まれるニコチンが血管を収縮させると、血流が悪くなり、冷え性を引き起こしてしまうでしょう。
また、一時的な血管の収縮だけでなく、動脈硬化が進行する点にも注意が必要です。
ストレス
ストレスを感じると、自律神経の一種である「交感神経」が優位になり、脈拍が速まったり緊張状態に陥ったりする場合があります。
同時に血管が収縮し、手足の血流が悪くなるため、冷え性を自覚する方が多いでしょう。
女性の場合

基本的には男性と同じく運動不足・喫煙・ストレスが冷え性の原因となります。
しかし、女性特有の原因によって足の冷えが起きている可能性もあるため、これからご紹介する4つの原因をチェックしていきましょう。
基礎代謝の低下
男性と比較して筋肉量の少ない女性は、相対的に脂肪量が多く、基礎代謝が低い場合が多いでしょう。
代謝が低い分体温も下がりやすく、冷え性が起こりやすいといった特徴があります。
食生活
極端なダイエットをしている女性などは、栄養バランスが偏り、基礎代謝の低下や血流の悪化を招くことがあります。
鉄分不足
月経などで鉄分が不足しやすい女性は、貧血による冷え性を起こしやすいといえます。
身体の冷えだけでなく、倦怠感や立ちくらみを起こす場合があるため、日頃から鉄分を積極的に摂取することが大切です。
脂肪量が多い
女性はホルモンの影響により、男性よりも脂肪量が多くなりやすいといえます。
筋肉は熱を産生するはたらきがありますが、脂肪が多いとこのはたらきが阻害され、身体が温まりにくくなるでしょう。
足は冷たいのに顔がほてる・手が温かいのはなぜ?

足が冷たいにもかかわらず顔がほてったり、手が温かかったりする場合は、体温調節機能が関連していると考えられます。
体内では末端よりも臓器への血流が優先されるため、寒い環境では足への血流が低下し、冷たく感じやすいでしょう。
一方顔周辺は太い血管が密集しており、脳への血流も維持されているため、ほてりやすくなります。
上半身と下半身では上半身の方が血流の低下が起きにくいため、足よりも手の方が温まりやすいのです。
足が冷たいのに汗をかくのは病気?

足が冷たいときに汗をかく方は、これからご紹介するいくつかの病気を疑うことをおすすめします。
自律神経失調症
私たちの身体は交感神経・副交感神経の2つがバランス良くはたらくことによって機能を維持しています。
これら自律神経のバランスが崩れると、寒冷時でも過剰に汗をかく場合があるでしょう。
多汗症
足が冷たいにもかかわらず汗を大量にかいてしまう場合は、多汗症という病気の可能性もあります。
手足や脇の下など汗腺が密集している部位は汗をかきやすいため、自覚症状がある方は医療機関を受診すると良いでしょう。
甲状腺機能異常
甲状腺のホルモンが増加すると、代謝が活発になり、発汗量が多くなります。
一方で甲状腺のホルモンが低下してしまうと代謝が低下し、足の冷えが起こりやすくなるでしょう。
どちらが多くても少なくても問題となるため、自身の甲状腺機能に不安がある方は医師への相談が必要です。
神経障害
パーキンソン病や糖尿病などの病気によって自律神経の機能が低下すると、足の冷え、発汗などの症状を起こす場合があります。
関連記事:汗っかきを根本から改善!体質を整える生活習慣と対策を解説
足が冷たいときに考えられる病気とは
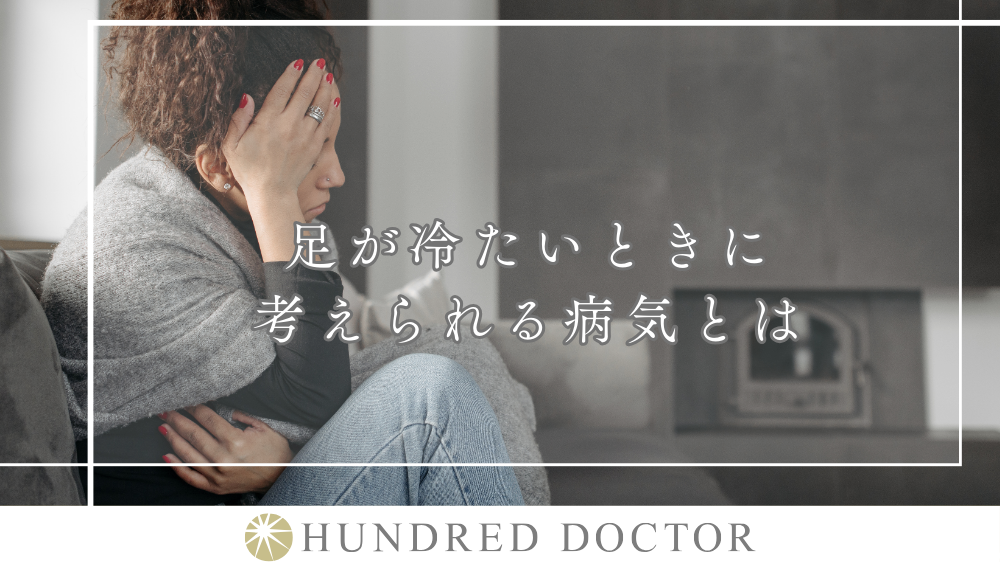
足が冷たい状態は、その多くが寒い環境に身体が対応した結果と考えられます。
しかし中には病気が隠れている場合もあるため、他の症状や体調不良を感じる場合は、なるべく早く医師へ相談しましょう。
低血圧
低血圧の方は血液を送り出す力が弱く、手足の血流が低下してしまいます。
足の冷えを感じやすいほか、立ち眩みや嘔気・めまいなどの症状を引き起こす場合があるでしょう。
貧血
貧血は酸素を全身に運ぶヘモグロビンが不足する病気です。
ヘモグロビンが少ないと末端に酸素や栄養が行き渡らなくなるため、血流が低下し、手足が冷えやすくなるでしょう。
そのほかにも倦怠感や立ち眩みなどの症状が出る場合もあります。
膠原病
膠原病とは自分の体の組織に対して抗体ができる自己免疫の病気です。
血管や結合組織に影響が及び、血流が悪くなることで、手足の冷えを感じるケースが多いといえます。
甲状腺機能低下症
甲状腺機能が低下すると代謝が低下し、足が冷たくなることがあります。
閉塞性動脈硬化症
高血圧の放置や長期間の喫煙によって、全身の毛細血管が細くなったりしなやかさを失ったりする病気です。
血管が細くなることによって血流が悪くなり、足の冷えを引き起こす可能性があります。
足が冷たいときの改善対策

続いて、足の冷たさを改善する方法について、8つのポイントから解説していきましょう。
保温
暖房器具を使用したり、厚手の靴下を着用したりといった工夫を取り入れ、足元を温かく保ちましょう。
適切な服装
暖かい服を着て身体全体を温かく保つことはもちろん、汗が乾く際に体温を奪われないよう、暑すぎないように調節することが大切です。
運動
軽い有酸素運動を行うことで、血行が改善し、足の冷えを軽減することができます。
散歩やストレッチなど、無理なく続けられる運動を始めてみることがおすすめです。
足浴
足浴を行うと、足の血流と冷えの両方を改善することができます。
熱すぎるお湯は肌の乾燥を招いたり、足元が急激に冷えたりする原因となるため、あくまでもぬるま湯を使ってゆったりと楽しむと良いでしょう。
マッサージ
足のマッサージを受けることで、筋肉の緊張をほぐし、血行を改善できます。
適切な栄養摂取
鉄分やビタミンB12など、貧血の原因となる栄養素を適切に摂ることが大切です。
ストレス管理
ストレスによって血管が収縮することがないよう、定期的にストレスを発散したり、ストレスフルな環境を改善したりすると良いでしょう。
禁煙
喫煙している場合は、本数を減らしたり、これを機に禁煙を目指したりすることをおすすめします。
まとめ
今回は足が冷たい時の原因や考えられる病気・改善方法などについて詳しく解説しました。
足の冷えの原因は男女別にも違いが見られます。
まずは健康的な生活習慣を身につけて、足を冷やしすぎないようにすることから始めましょう。
改善方法などを試してみてもなかなか冷えが改善されない場合は、かかりつけの医師へ相談することが大切です。
参考文献
▶冷え性|ふくおかクリニック
▶効果的な冷え性対策とは?男性も必見!朝晩の通勤で冷えないための秘策|アンファー からだエイジング
▶手足の冷え(冷え性)の原因|第一三共ヘルスケア