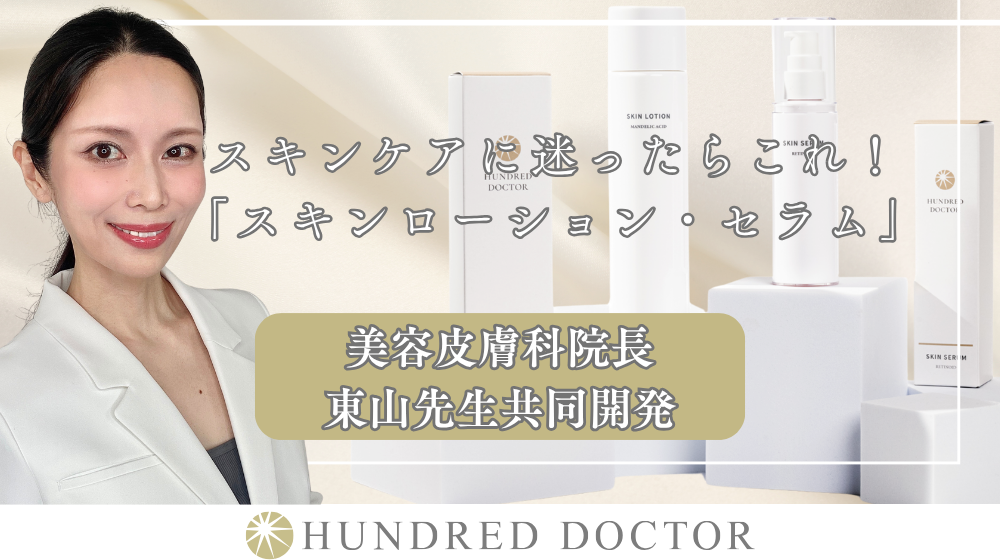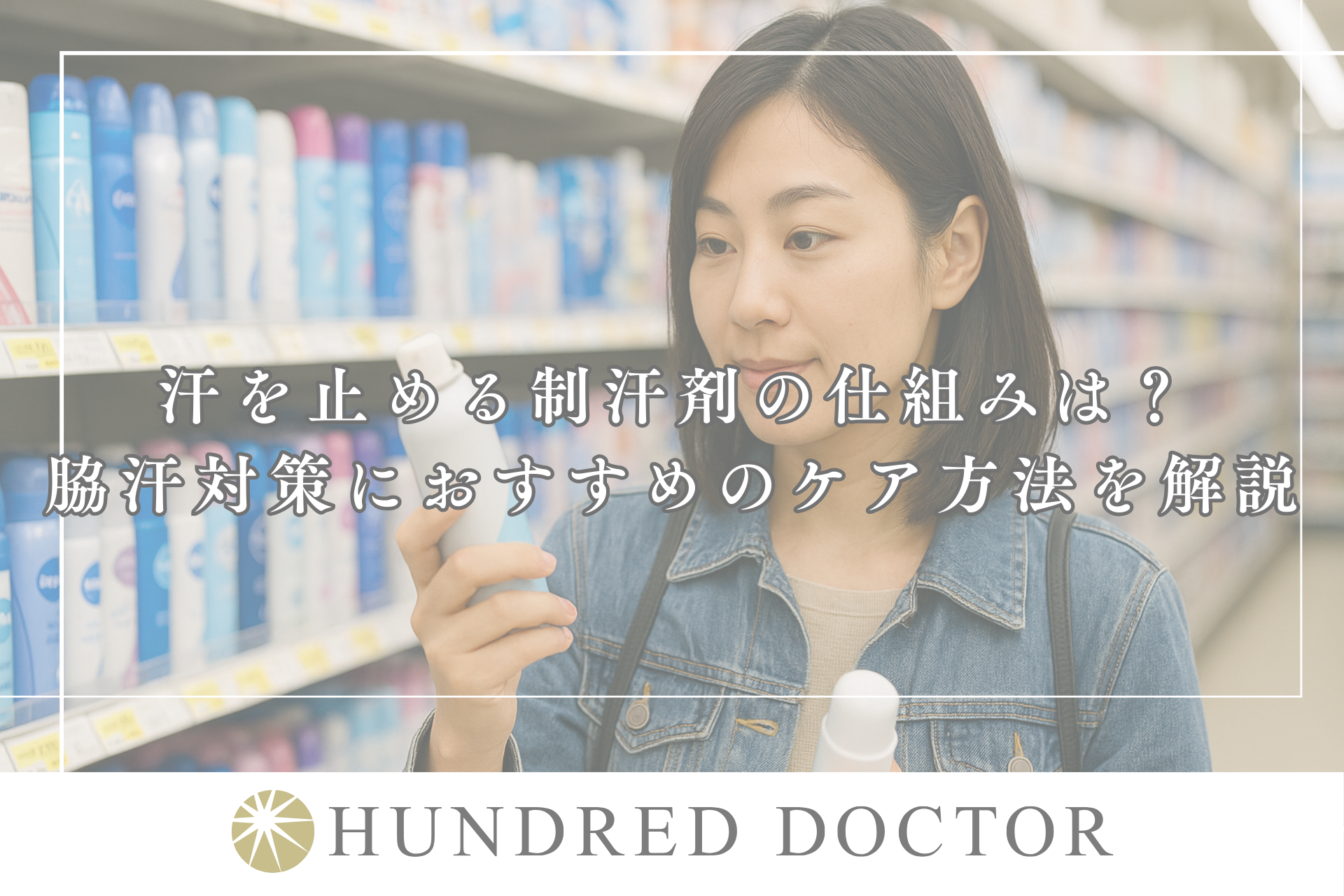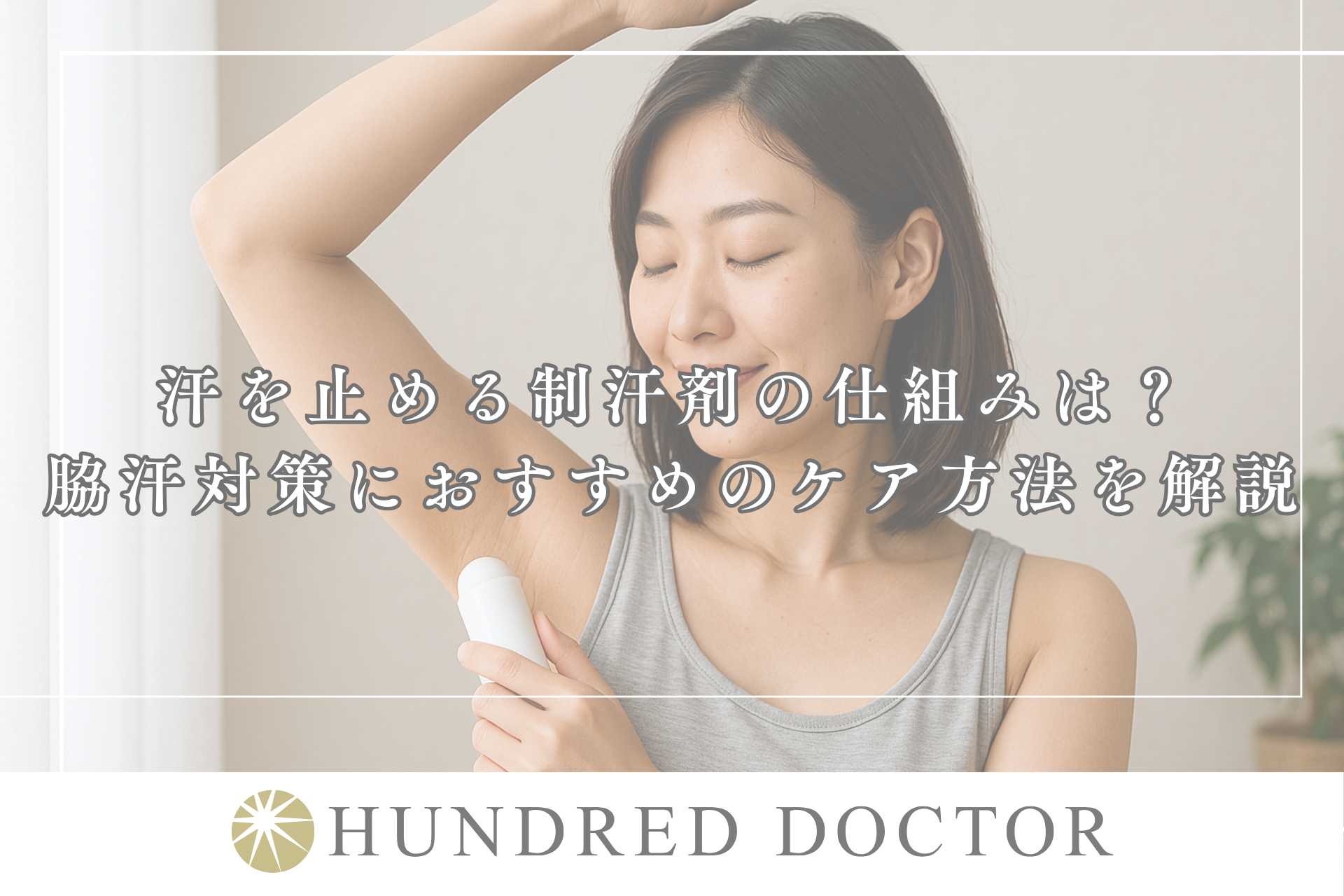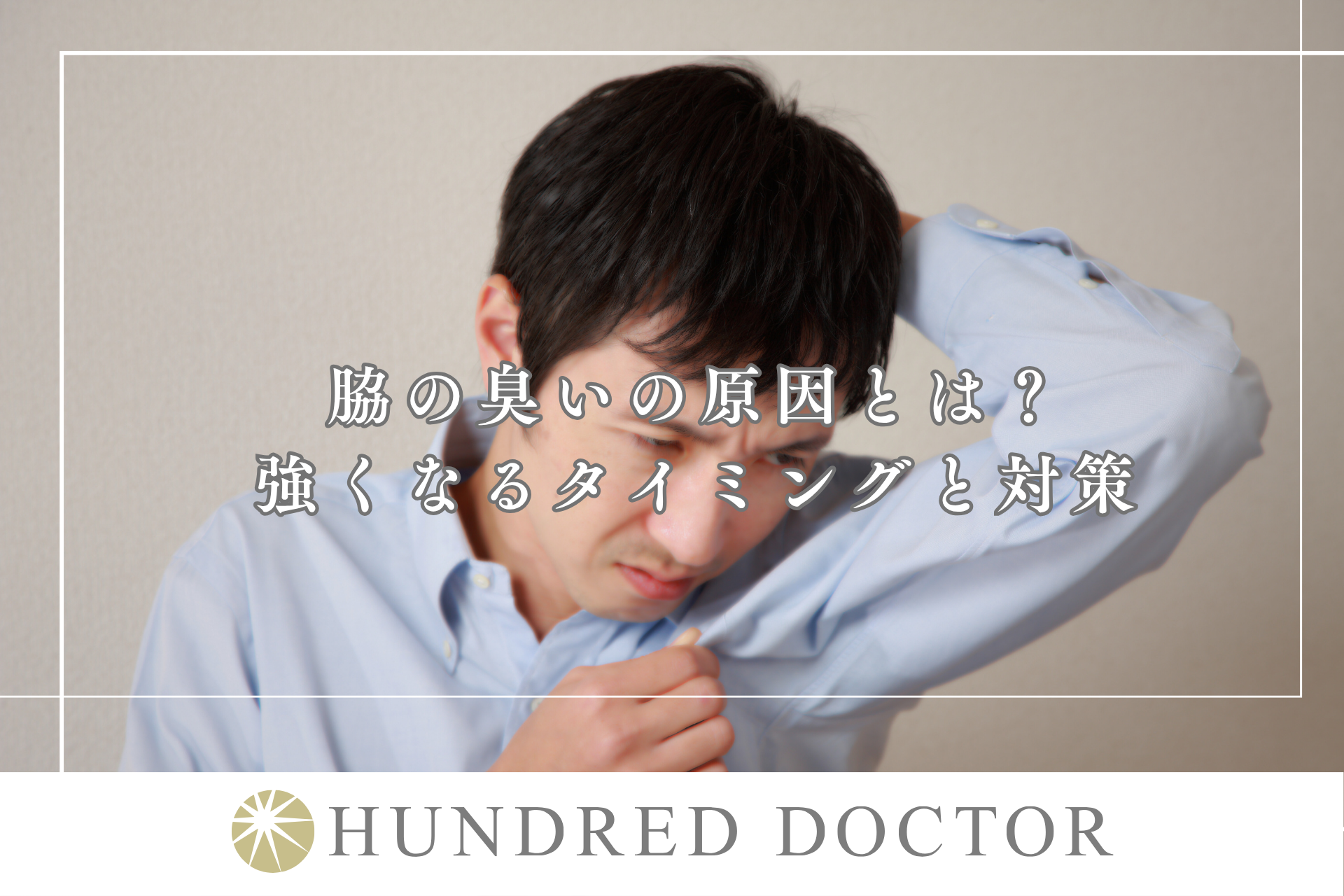
脇の臭いの原因とは?強くなるタイミングと対策をわかりやすく解説
脇の臭いが気になっても、原因がはっきり分からず悩む人が少なくありません。
体質だけでなく、生活習慣や日々の行動が影響しているケースも多く見られます。
本人が気が付かないうちに、対策が遅れ臭いが強くなることも。
本記事では脇の臭いで考えられる原因から強くなるタイミング、効果的な対策まで分かりやすくご紹介します。

Contents
脇が臭くなる原因とは
脇の臭いの背景には、さまざまな原因があります。
体質だけでなく生活習慣が臭いを強めている場合もあるため、原因を知ることが対策の第一歩です。
体質によるニオイ
人の身体には水分が多く臭いの少ない「エクリン汗腺」と、べたべたとして臭いの強い「アポクリン汗腺」が存在します。
アポクリン汗腺の方が活発にはたらいている人の場合、脂質やタンパク質を含む汗が出やすく、皮膚の常在菌と反応して独特の臭いが生じます。
このように体質によって汗が強く臭う方を「ワキガ体質」と呼ぶこともあります。
生活習慣によるニオイ
不規則な生活や脂質の多い食事・ストレスの多い生活を続けていると、汗や皮脂の成分が変化し、臭いが強くなることがあります。
元々アポクリン汗腺のはたらきが活発な方はもちろん、そうでない方でも汗が臭いやすくなります。
関連記事:ワキガになる原因とは|どんな匂い?治療法や治し方について解説
脇の臭いは自分で気づきにくい?
基本的に、自らが発する臭いは自分で気が付きにくいといった特徴があります。
脇の臭いだけでなく、頭皮の臭いや口臭なども自分の臭いレベルを正しく把握することは難しいでしょう。
これは嗅覚が長時間同じ臭いにさらされることで、鼻が臭いに慣れていることが原因だといえます。
特に脇の場合は服の内側に臭いがこもり、自分の鼻まで届きにくい点に注意が必要です。
自分よりも他人の方が先に気が付いてしまうと、対策が遅れるだけでなく、周りからの印象悪化にもつながります。

脇の臭いが強くなるタイミングとは
脇の臭いは常に同じレベルで発生しているわけではなく、タイミングによって強くなったり弱くなったりします。
食生活の変化
動物性脂肪や香辛料の多い食事を頻繁に摂ると、汗に皮脂が混ざりやすく、臭いが強まることがあります。
ストレス
緊張やストレスを感じると、交感神経が刺激され、アポクリン汗腺のはたらきが活発になります。
飲酒・喫煙
アルコールやタバコの成分が汗に混ざると、独特の臭いが発生します。
アルコールの場合は血行が促進されて発汗量が増え、臭いがこもる原因になります。
一方、喫煙は血液やリンパの流れを阻害するはたらきがあるため、通常時と比べて老廃物がうまく排出されません。
運動時や暑い部屋などで汗をかいた場合、老廃物が同時に排出され、臭いが強まりやすくなります。
汗の量の変化
夏場や運動後など、汗の量が増えるタイミングでは臭いも発生しやすくなります。
汗をかいてそのままにしておくことで、雑菌が繁殖し、さらなる臭いの悪化につながります。
ホルモンバランスの変化
思春期や更年期・月経前などでホルモンバランスに変化があると、皮脂や汗の分泌が増え、臭いが強くなる傾向があります。
遺伝
家系にワキガの人がいるなど、遺伝で汗が臭いやすい方もいます。
元々アポクリン汗腺の量が多い方などは、医療機関にて切除する方法もあります。
関連記事:脇の皮脂詰まりで臭いが強くなる?臭いを防ぐケア方法と対策とは?
脇の臭いを防ぐための対策
脇の臭い対策は、日常的なケアと生活習慣の見直しの両方からアプローチすることが大切です。
デオドラントや制汗剤の活用
殺菌成分や制汗成分を含むデオドラントアイテムがおすすめです。
スプレータイプ・パウダータイプ・拭き取りタイプなどさまざまな製品が登場しています。
日常的なケア方法の見直し
毎日の入浴で脇をしっかり洗ったり、汗をかいたときはすぐに拭き取ったりといった習慣が効果的です。
蒸れやすい服装は避け、通気性のよい素材でできた衣類を選びましょう。
汗や皮脂を抑える生活改善
脂質の多い食事を控え、ビタミンB群やビタミンC・ビタミンEを意識して摂取することで皮脂の抑制につながります。
良質な睡眠やストレス管理を徹底し、アポクリン汗腺が活性化しないよう注意が必要です。

脇の臭いでお困りならHUNDRED DOCTORのわき用クリーム
HUNDRED DOCTORでは、医師と共同開発したドクターズコスメを販売しています。
医学的知見に基づき、ニオイの原因菌や発汗のメカニズムに着目。
成分を厳選し、肌へのやさしさと確かな持続力を両立させました。
本来、汗そのものはほぼ無臭で、皮膚の常在菌が汗や皮脂を分解する過程で、においとして感じやすい成分が生まれます。
つまり、汗 × 皮脂 × 菌の組み合わせが、臭いのもととなります。
そこでHUNDRED DOCTORのわき用クリームは、
- 原因菌の繁殖を抑える成分で、ニオイの発生を根本からケア
- 皮脂と汗のバランスを整える処方で、菌が繁殖しにくい肌環境をキープ
- 長時間持続するクリーム設計で、朝のケアだけで日中も快適にサポート
敏感肌にも配慮し、ベタつきにくく使いやすい処方だから、毎日のケアを負担なく続けられます。
汗の臭いが気になるこの季節、セルフケアとしてわき用クリームをお試しください。
また、HUNDRED DOCTORではわき用クリームに関する電話医療相談を無料で行っております。
使用前や使用中など気になることがあればお気軽にご相談ください。
電話受付時間:平日 10:00~18:00

まとめ
脇の臭いは、体質だけでなく生活習慣や行動が大きく関係しています。
まずは原因を正しく知り、状態に合わせたケア方法を試すことで、夏場や運動時の臭い軽減を目指せます。